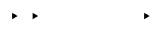車のヘッドライトを消し忘れてしまい、バッテリー上がりを経験したことはないでしょうか。
バッテリーが上がってしまうと、エアコンやオーディオが使用できなくなるのはもちろん、エンジン始動に不可欠なセルモーターも作動しなくなるため、走行不能に陥ってしまいます。
この記事では、ヘッドライトのつけっぱなしでバッテリーが上がってしまう原因や、その対処法について詳しく解説します。
バッテリー上がりを解決してくれる業者も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
ヘッドライトのつけっぱなしでバッテリーが上がる
エンジン停止後にヘッドライトをつけっぱなしにすると、バッテリーの電力消費が続くため、最終的にバッテリー上がりを引き起こします。
ここでは、ヘッドライトのつけっぱなしによるバッテリー上がりについて解説します。
- バッテリーが上がるまでの時間
- ハイブリッド車のバッテリー上がりについて
ひとつずつ確認しましょう。
バッテリーが上がるまでの時間
ヘッドライトをつけっぱなしにした場合、バッテリー上がりは一般的に約3~5時間で発生すると言われています。
ヘッドライトをつけっぱなしにすると、バッテリーが放電して最終的に上がってしまうので気をつけましょう。
この主な要因は次の2つです。
- ヘッドライトの電力消費
- バッテリーの経年劣化による容量低下
たとえば、40Ahのバッテリーを搭載した車両の場合、ヘッドライトの1時間あたりの消費電力が約8〜9.5アンペアのため、理論上は約5時間で完全に放電します。
ただし、バッテリーが常に満充電であるとは限りません。
また、ハザードランプやルームランプなども同時に点灯している場合は、さらに短い時間でバッテリーが上がる可能性があります。
バッテリー上がりを防止するためには、運転後は必ずすべてのランプの消灯を確認する習慣を徹底しましょう。
ハイブリッド車のバッテリー上がりについて
ハイブリッド車でバッテリー上がりを起こし走行不能となるのは、主に補機用バッテリーのトラブルによるものです。
ハイブリッド車は、下記の二つのバッテリーを搭載しています。
- 駆動用バッテリー: 走行モーター用
- 補機用バッテリー: システム全体用
ヘッドライトのつけっぱなしなどでバッテリー上がりを起こしやすいのは、補機用バッテリーです。
補機用バッテリーが上がると、たとえ駆動用バッテリーの残量が十分でも走行できなくなります。
また、基本的に駆動用バッテリーから補機用バッテリーへの充電はできません。
たとえば、「駆動用バッテリーの残量表示は十分なのに、エンジンがかからない」といった状況は、補機用バッテリーのバッテリー上がりを示唆する典型的なケースです。
ハイブリッド車は、駆動用バッテリーが正常でも、補機用バッテリーが上がると走行不能になる点が、ガソリン車と異なります。
ハイブリッド車のバッテリー上がりは、補機用バッテリーの仕組みを理解し、ヘッドライトのつけっぱなしに気をつけ、定期的な点検を実施しましょう。
バッテリーが上がるその他の原因
ヘッドライトのつけっぱなし以外でも、バッテリー上がりは発生します。
その原因について、3つ解説します。
- 長い間運転していない
- バッテリーの寿命
- バッテリーが上がりやすい時期
それぞれ詳しく見ていきましょう。
長い間運転していない
長期間車を運転しないと、運転不足による充電不足や、バッテリーの自然放電でバッテリー上がりが発生します。
対策としては、バッテリーのマイナス端子を外す、またはバッテリー本体からの取り外しが有効です。
車のバッテリーは、走行中にオルタネーターが発電することで充電されます。
しかし、しばらく運転しない状態が続くと、オルタネーターによる充電が行われません。
その結果、バッテリーは自然放電という現象によって徐々に電気を失い、最終的にバッテリー上がりを引き起こします。
この状態で放置すると、いざ車に乗ろうとした際に「バッテリーが上がってエンジンがかからない」という事態になりかねません。
長期間車を運転しない時は、バッテリーの端子を外すか、バッテリー本体を分離するのが賢明と言えるでしょう。
バッテリーの寿命
バッテリーの寿命は一般的に2~5年であり、寿命が近づくとさまざまな症状が現れます。
バッテリーは使用とともに劣化し、充電しても満充電にならず、最大容量が減少します。
バッテリーの寿命が近づくと、下記のような兆候が現れるため注意しましょう。
- エンジンの始動が鈍くなる
- パワーウインドウの動きが遅くなる
- ヘッドライトが以前より暗くなる
- バッテリー本体が膨らんでくる
- バッテリーの端子に白い粉が付着する
バッテリーの寿命は、テスターを使用した電圧測定で確認できます。
電圧の正常値は、下記の通りです。
- エンジン停止時 : 12.4V以上
- エンジン回転時 : 13.5~14.7V
停止時に正常値以下なら放電の可能性があり、充電で回復する場合があります。
しかし、エンジン回転時に異常値を示す場合は、バッテリーだけでなくオルタネーターやレギュレーターの故障も疑われます。
バッテリーに寿命の兆候が見られたり、電圧測定で異常が確認された場合は、早めのバッテリー交換がおすすめです。
特にエンジン回転時の異常値は、放置するとバッテリーだけでなく車両全体の故障につながる可能性があるため、速やかに点検・修理を行いましょう。
バッテリーが上がりやすい時期
バッテリーは、夏と冬に上がりやすいです。
夏は、高温によってバッテリー内部の化学反応が活発になり、自然放電が進みやすくなります。
一方冬は、低温によりバッテリー液の化学反応が弱まり、充電効率が低下する上、電力容量も減少します。
夏冬共通して、エアコンの使用頻度が高まることも、バッテリーの電気を大きく消費する要因です。
夏の暑い日に、駐車中や渋滞による長時間のエアコン使用は、バッテリー上がりの原因となります。
冬の寒い朝に、バッテリーの性能低下によってエンジンがかかりにくくなる経験をする方も少なくありません。
そのため、夏と冬はバッテリーの状態に特に注意し、早めの点検や適切な使用を心がけることが重要です。
バッテリー上がりの確認方法
バッテリー上がりかどうかは、スターターの反応と室内灯・警告灯の状態を確認することで判断できます。
バッテリーが上がると、エンジンを始動させるための十分な電力が供給されなくなるため、特定の症状が現れます。
バッテリーが上がっている場合の具体的な症状は下記の通りです。
スターターの場合
- スターターが回らない
- スターターの回転に勢いがない
- スタートボタンを押してもスターター音がしない
室内灯・警告灯の場合
- 明かりが全く点灯しない
- 明かりが普段より暗い
エンジンがかからない際は、これらの症状に当てはまるか確認をしましょう。迅速な判断が、スムーズな対処へと繋がります。
バッテリーが上がったときの対処方法

バッテリーが上がってしまった場合、自然に回復することはありません。
対処をしない限りエンジンはかからず、ずっと車に乗れない状態が続きます。
そのため、バッテリーを回復させるために、下記のような対処を行いましょう。
- ブースターケーブルで充電する
- ジャンプスターターで充電する
それぞれについて、解説します。
ブースターケーブルで充電する
バッテリー上がりには、ブースターケーブルと救護車を使った充電が有効です。
ブースターケーブルは、正常なバッテリーを持つ救護車から電気を分けてもらい、バッテリー上がりの車を一時的に始動させるための道具です。
救護車は電圧が同じで、車格が同等以上である必要があります。
接続時には、両車の電気系統トラブルを防ぐため、ライトやエアコンなどをOFFにし、エンジンは切っておきましょう。
また、後続車の衝突を防ぐため、安全な場所に停車し、三角板などを設置してください。
ブースターケーブルの接続は、下記の順番で行います。
- 自分の車のプラス端子に赤いケーブルを繋げる
- 救護車のプラス端子に赤いケーブルを繋げる
- 救護車のマイナス端子に黒いケーブルを繋げる
- 自分の車のマイナス端子に黒いケーブルを繋げる
ケーブル接続後、救護車のエンジンをかけ、約5分ほど待ちます。
その後、バッテリーが少し充電されたら、自分の車のエンジンを始動させましょう。
ケーブルを取り外す際は、接続時と逆の順番で行ってください。
エンジンがかかっても、すぐにエンジンを切るとバッテリーの充電が不十分なため、再びエンジンがかからなくなる可能性があります。
そのため、エンジン始動後はしばらく車を走らせて、車の発電機であるオルタネーターでバッテリーをしっかりと充電しましょう。
ジャンプスターターで充電する
ジャンプスターターは、救援車やロードサービスなしでバッテリー上がりを解消できる便利なアイテムです。
モバイルバッテリーの電気を利用するため、バッテリー上がりの車に直接充電できます。
ただし、使用前にジャンプスターターの本体をフル充電しておくことが重要で、容量が不足していると正常に充電できない可能性があるため、注意しましょう。
充電の手順は、下記の通りです。
- ジャンプスターターのケーブルを車のバッテリー端子に繋げる
- ジャンプスターターのケーブルをモバイルバッテリーに繋げる
- 車のエンジンをかける
ケーブル接続後、1分ほど経ってからエンジンをかけましょう。
エンジンがかかれば、車のバッテリーは充電されています。
ケーブルは接続と逆の手順で外し、その後30~60分程度走行してバッテリーを十分に充電してください。
エンジン始動後すぐに停止すると、再始動できない場合があります。
ジャンプスターターがあれば、いざという時に自分でバッテリー上がりの対処ができます。
バッテリー上がりを解決してくれる業者
バッテリー上がりを解決してくれる代表的な業者を5つ紹介します。
- JAF
- 保険会社のロードサービス
- カーバッテリー業者
- ディーラー
- ガソリンスタンド
自己解決が難しい場合の参考にしてください。
JAF
JAFはロードサービスのひとつです。
会員であればバッテリー上がりを無料で対応してもらえますが、非会員は有料となります。
JAFは、年会費・入会費を支払うことで会員になれます。
会員はバッテリー上がりだけでなく、パンク修理やガソリン切れといった多岐にわたるカーサービスを無料で利用できる点が大きなメリットです。
連絡一本で迅速に駆けつけてくれるため、車を日常的に使う方にとって、万が一の際の大きな安心材料となるでしょう。
非会員の方も、JAFのサービスを利用できますが、バッテリー上がりの対応には、1回あたり10,000円以上の費用がかかる点に注意が必要です。
また、バッテリー交換が必要となった場合は、さらに高額な費用が発生する可能性があります。
このように、JAF会員は、バッテリー上がりを含むさまざまな車のトラブルに対し、費用面でも精神面でも大きなメリットをもたらします。
車を頻繁に利用する方は、ぜひJAFへの入会を検討してみてください。
保険会社のロードサービス
自動車保険の付帯ロードサービスは、バッテリー上がりの際に無料で充電してくれる便利な選択肢のひとつです。
多くの自動車保険にはロードサービスが付帯しており、加入していればこのサービスを利用できます。
バッテリー上がり時の充電は無料で行われますが、バッテリー交換には費用が発生する点に注意が必要です。
ロードサービスを利用しても翌年の等級や保険料には影響がないため、安心して利用できます。
ただし、無料対応回数については事前に確認しておくと良いでしょう。
自身が加入している自動車保険にロードサービスが付帯しているかを確認し、いざという時のバッテリー上がりに備えましょう。
カーバッテリー業者
JAFや保険ロードサービス以外にも、バッテリー上がりを解決してくれる専門業者がおり、いざという時の頼りになります。
これらの業者は「バッテリー上がり 業者」などで検索すれば見つかります。
24時間365日対応していることが多く、土日祝日や早朝深夜でも利用可能です。
万が一の際に備えて、連絡先を控えておくと良いでしょう。
費用は8,000円から10,000円程度が目安ですが、サービス内容や出張費、夜間割増料金は業者によって異なります。
バッテリー交換が必要な場合は、さらに高額になる可能性があります。
依頼する前に、費用やサービス内容の詳細な確認が大事です。
専門業者を上手に活用すれば、バッテリー上がりの際も、迅速かつ確実に問題を解決できるでしょう。
ディーラー
ディーラーは、営業時間内であればバッテリー上がりの対応が可能です。
車を購入したディーラーが近くにあれば利用できます。
バッテリー充電は有料ですが、短時間の充電であれば無料で対応してくれる場合もあります。
ただし、遠方からの出張には、別途費用がかかる場合があるため、注意が必要です。
急なバッテリー上がりで困った際は、まず購入したディーラーに連絡し、対応の可否と料金について問い合わせてみましょう。
特に、出張費や短時間充電の無料対応の有無は確認が必要です。
ディーラーは車の専門知識が豊富ですが、営業時間や費用体系を理解した上で利用を検討してください。
ガソリンスタンド
ガソリンスタンドでは、バッテリー上がりの充電サービスを提供しており、持ち込みまたは出張での対応が可能です。
バッテリーが上がって車が動かせない場合でも、ガソリンスタンドによっては出張対応してくれるため、いざという時に頼りになります。
また、スタンドに車やバッテリーを持ち込めば、その場で迅速に充電してもらえる利便性もあります。
持ち込みでの充電は数千円程度、出張対応の場合は10,000円程度の費用がかかるのが一般的です。
費用は事前に確認しておくと良いでしょう。
身近なガソリンスタンドは、バッテリー上がりの際に迅速に対応してくれる便利な選択肢のひとつです。
バッテリー上がりを防ぐ方法

バッテリー残量が少なくなってくると、いくつかの予兆が見られます。
たとえば、エンジンがかかりにくい、カーナビやライトが暗いといったときは注意が必要です。
また、パワーウィンドウの開閉が遅い、バッテリー警告灯が点いているときも同様に注意しましょう。
ヘッドライトをつけっぱなしにしない以外にも、バッテリー上がりを防ぐ方法が3つあります。
- 定期的に車を走らせる
- バッテリーのケーブルを外す
- バッテリー液を確認する
それぞれについて、詳しく解説します。
定期的に車を走らせる
バッテリー上がりを防ぐには、定期的に車を走行させると効果的です。
車は、走行中にオルタネーターが発電してバッテリーを充電するため、運転しないと充電されず、自然放電によってバッテリー残量が減少します。
バッテリーを充電するには、少なくとも毎週1回30分以上の運転がおすすめです。
運転機会が少ない場合は、1回30分以上のアイドリングでも少しずつ充電できます。
定期的な走行やアイドリングでバッテリーを充電し、バッテリー上がりを未然に防ぎましょう。
バッテリーのケーブルを外す
長期間車を運転しない場合、バッテリーのマイナス端子を外すことでバッテリー上がりを効果的に防げます。
ケーブルを外すと、車載システムによる微細な電力消費(自然放電以外)が抑えられ、バッテリーの急激な消耗を回避できます。
この方法であれば、約1ヶ月程度車を運転しなくても、バッテリーが上がる可能性を大幅に低減できるでしょう。
ただし、1ヶ月以上運転しない場合は、バッテリー上がりのリスクが高まります。
そのため、長期間車に乗る予定がない場合は、バッテリーのマイナス端子を外すのが賢明な対策です。
バッテリー液を確認する
バッテリー液の定期的なチェックと補充は、バッテリーの劣化を防ぎ、寿命を延ばすために非常に重要です。
バッテリー液が不足すると、バッテリーの劣化が早まります。
水分蒸発や電気分解、液漏れなどによってバッテリー液は徐々に減少するため、3ヶ月に1回程度の定期的な残量チェックが大事です。
バッテリーの側面には「UPPER LEVEL」と「LOWER LEVEL」の目印があり、この間に液があれば適正量です。
残量チェックは、ボンネットを開けてバッテリーを横から見て確認しましょう。
もし下限位置よりも液が減っている場合は、補充が必要です。
作業手順は下記の通りです。
- バッテリー液の注入口を開ける
ドライバーで開けるのが難しい場合は、硬貨を使うと簡単に開けられる - ゴム手袋を装着する
注入口に希硫酸が付着している場合があるため、要注意 - 上限の下までバッテリー液を充填する
すぐに用意できない場合は蒸留水で代用可能
バッテリー液の適正量を保つことで、バッテリーの性能を維持し、予期せぬトラブルを未然に防げます。
まとめ
車のヘッドライトをつけっぱなしにするとバッテリー上がりにつながります。
運転後は必ず消灯する習慣をつけましょう。
また、長期間車を運転しなかったり、バッテリーが寿命を迎えていたりする場合もバッテリー上がりは発生します。
これを防ぐには、定期的なバッテリーチェックが重要です。
バッテリー液が減っていれば補充し、寿命がきたバッテリーは迷わず交換してください。
これらの対策を講じれば、バッテリー上がりによる予期せぬトラブルを回避し、快適なカーライフを送れます。
日頃からの少しの気遣いが、安全なドライブへとつながるでしょう。