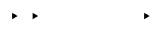駐車場などを走行中、「ゴンッ」と車内にぶつかった音がしたのに、車を見ても傷がなかった、という経験はありませんか?
音がしたのに傷がない原因は「小石の跳ね」や「整備不良」などのケースもあり、音がしても、実際はぶつかっていない場合もあります。
この記事では、車をぶつけたような音がしたけど車両の傷がない場合に行う、正しい対応と再発防止策などを解説します。
今まで同様の経験がない方も、今後運転する中で同じ事態に巻き込まれるかもしれませんので、皆さんご覧ください。
車からぶつかった音がしたのに傷がないのはなぜ?考えられる原因
車を運転中にぶつかった音がしても、実際には接触していない場合があります。
ここでは、車から衝突音がしたのに傷がないときに考えられる原因を4つ解説します。
- バンパーなど外装部品への軽い接触
- 小石や落下物の跳ね
- 風で飛ばされた物が車体に当たった
- 車の故障や整備不良
ぶつかった音がしても慌てず、まずは落ち着いて原因を確認することが大切です。
バンパーなど外装部品への軽い接触
音がしたのに車に傷が見当たらない場合、外装の柔らかい部分に軽く接触しただけの可能性があります。
昔の車は金属製バンパーが一般的でしたが、現在は樹脂製が主流です。

また近年のSUVブームにより、フェンダーやサイドモールなどにも、黒い樹脂製パーツが装着されている車種が増えています。

これらの樹脂パーツは弾力性が高く衝撃を吸収するため、軽く当たった程度ではへこんでも元に戻ってしまいます。
そのため、低速で接触したときなど、ぶつかった音がしても塗装や形状に大きな影響が出ないことがあります。
ただし、内部には見えない損傷が隠れていることもあるため、見た目に変化がなくても整備工場で点検しておくと安心です。
小石や落下物の跳ね
走行中に「コンッ」という音がした場合、路面の小石や落下物が跳ねた音かもしれません。
タイヤが巻き上げた石が、車体側面のフェンダーやタイヤハウスに当たると、音が車内まで響くことがあります。

特に高速道路や砂利道を走行中には、このような音が発生しやすい傾向にあります。
この場合、音が大きくても、実際には外装への損傷がないことがほとんどです。
ただし落下物を踏んだ場合はタイヤやホイールに小さな傷がついていたり、パンクしている可能性があるので、車体の下部やタイヤ周辺を確認しておくとよいでしょう。
風で飛ばされた物が車体に当たった

強風の日や台風のあとなどは、風で飛ばされた物が車体に当たることがあります。
このとき当たった音が車内に響き渡ることで、自分の運転による衝突音と勘違いするケースも少なくありません。
実際にはビニール袋や軽い枝などが当たっただけで、大きな傷が残らないことが多いです。
不安を感じたら一度停車し、車体全体を目視で確かめると安心できます。
車の故障や整備不良
車の故障や整備不良によって異音が発生し、その音がぶつかった音に聞こえる場合があります。
このような異音は時として、振動や衝撃を伴うこともあるため、余計に自車がぶつかったように感じがちです。
詳細は後述しますが、実際に筆者も同様の体験をしており、実際に異音と衝撃を感じました。
このように、ぶつかった音などを車内で感じても、その原因は車の故障や整備不良が原因である場合があります。
車をぶつけたかも?傷がなくてもまず確認すべきこと

「もしかして、ぶつけたかも」と不安に感じたときこそ、慌てず状況を冷静に見極めることが大切です。
ここでは、車をぶつけたかもしれない場合に、冷静に確認すべき3つのポイントを紹介します。
- 愛車の状況
- 他車や壁、ポールなどの周囲のもの
- ドライブレコーダーの映像
愛車の状況
まずは、自分の車のバンパー・フェンダー・ドアミラーなど、外装全体を確認しましょう。
特にバンパーの角やドアの端は、接触しやすい部分なので、丁寧に調べる必要があります。
暗い場所ではライトを使い、光の当て方や角度を変えながら、小さな傷やへこみがないかも確認しましょう。

また、気になる箇所を手でなぞって細かい段差や、ざらつきを確かめるのも効果的です。
指先の感触で、光では分からない塗装の削れに気づくことがあります。
さらに、外観に異常がなくても、内部の固定具や衝撃吸収材が緩んでいる場合があります。
パーツの下や裏を軽く押して、ぐらつきや隙間がないかを確認すると安心です。
他車や壁、ポールなどの周囲のもの

自分の車に傷が見当たらなくても、周囲のものに接触している可能性があるため、確認が必要です。
特に駐車場や狭い道路では、壁やポール、ガードレールなどに接触した痕跡がないかを丁寧に調べましょう。
塗装の剥がれや擦れ跡、金属部分のわずかな変形などは、事実確認の手がかりになります。
また、近くに停車している車がある場合は、その車体にも異変がないか確認しておくと安心です。
自分の車に傷がなくても、相手の車体に跡が残っていることもあります。
特に、バンパーやドアの角など、当たりやすい位置を中心に確認しましょう。
ドライブレコーダーの映像
ぶつかった音がした瞬間の状況を把握するには、ドライブレコーダーの映像確認が有効です。
前後カメラを備えた機種であれば、車の動きだけでなく、周囲の状況も正確に確認できます。
映像から、実際に何かに当たったのか、あるいは音の原因が外的なものかを客観的に判断可能です。
また、他車が関係している場合には、ドライブレコーダーの記録が重要な証拠になることもあります。
録画データは上書きされやすいため、気になる場面があれば早めに保存しておきましょう
必要に応じてバックアップを取り、後日の確認に備えることが大切です。
車に傷がない場合でも注意!見落としやすいリスク
車の損傷は、必ずしも外から見て判断できるものではありません。
外見に傷がなくても、車体の内部に損傷が隠れていたり、わずかな接触でも「軽微な事故」と見なされる場合があります。
ここでは、そうした見落としやすいリスクについて、一つずつ詳しく解説します。
内部が損傷している場合がある

外装に傷がなくても、車の内部が損傷していることがあります。
バンパーの内側では、衝撃吸収材やステー(バンパーを固定する金具)が変形している場合があり、走行中の振動や異音につながることもあります。
さらに衝突防止や駐車支援などのセンサー類は、バンパーなどの外装部分に装着されているため、軽い接触でも影響を受けやすい構造です。
わずかな衝撃でも誤作動や感知のズレを引き起こし、障害物や人を正しく検知できず、事故や接触のリスクが高まります。
外観だけで判断せず、専門工場での点検を受けることが安全確保につながります。
軽微な接触事故に該当する場合がある
傷がなくても、相手の車や壁、ポールなどに当たった可能性がある場合は「物損事故」として扱われることがあります。
その場で傷がないから問題ないと立ち去ってしまうと、結果的に「当て逃げ」と判断される恐れもあるため注意が必要です。
特に駐車場など狭い場所では、軽い接触でも事故として扱われるケースが少なくありません。
また相手にぶつけられた場合でも、傷が見えないからと放置すると、後から事故として立証しづらくなり不利な状況に陥ることも。
見た目に問題がないようでも、まずは「事故の可能性がある」と考え、冷静に対応することが大切です。
車に傷がなくても警察・保険会社への連絡は必要?正しい判断と対応を解説
「車体に傷がないのに、警察や保険会社へ連絡が必要があるの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。
しかし、道路交通法第72条では、車やガードレールなどに接触した場合、事故の程度を問わず警察へ報告する義務が定められています。
また、相手が他車であった場合には、連絡を怠ると損害賠償や保険金請求ができなくなることも。
少しでも接触の可能性を感じたら、警察や保険会社に報告しておくことが、後々のトラブルを防ぐ鍵になります。
ここからは、それぞれへの連絡がなぜ重要なのかを詳しく解説します。
傷がない場合でも接触したら警察に報告

車や建造物への接触があった場合は、傷の有無にかかわらず、警察へ報告する義務があります。
これは道路交通法第72条で定められており、事故の大小に関係なく、運転者は「危険防止措置」と「事故の報告」を行わなければなりません。
この義務を怠って現場を離れると、当て逃げ(危険防止措置義務違反・報告義務違反)とみなされ、最大で1年以下の懲役または10万円以下の罰金・違反点数7点で免許停止処分となることもあります。
また駐車場などの私有地でも、通行目的で一般車両が出入りしている場所は「道路」とみなされ、道路交通法の適用対象です。
後のトラブル防止や責任の明確化のためにも、警察を呼んで記録を残しておくことが望ましいでしょう。
警察への報告により作成される「交通事故証明書」は、後日、修理費や損害賠償などを申請する際に必要な書類です。
もし事故後に相手と連絡が取れなくなった場合でも、証明書があれば自分の正当性を示す証拠となります。
「傷がない=問題ない」と自己判断せず、まずは警察へ報告し、事故の事実を明確にしておきましょう。
接触を確認したら保険会社にも連絡する
警察への報告とあわせて、保険会社への連絡も忘れてはいけません。
傷が見当たらなくても、後日になって相手から修理費を請求されたり、自車の損傷が見つかったりすることがあります。
事故直後には外見上問題がなくても、後から相手の車に小さな傷が発見され、のちに通知が来るケースも少なくありません。
また、自車のバンパー内部やセンサー部分に衝撃が残り、修理が必要になることも考えられます。
このようなとき、事故直後に保険会社へ報告し記録を残していれば、担当者が迅速に対応し、補償や手続きを円滑に進めることができます。
「傷がないから大丈夫」と終わらせず、警察への報告とあわせて保険会社にも連絡を入れることが、後々のトラブルや金銭的リスクを防ぐ最善の方法といえるでしょう。
同じ不安を繰り返さないために!再発防止策を紹介
接触やヒヤリとした経験をすると、「次は気をつけないと」と感じるものの、具体的に何をすればよいか迷う方も多いでしょう。
再発を防ぐには、運転時の習慣づけと車の装備を両面から見直すことが効果的です。
ここでは、今後同じ不安を繰り返さないために実践したい、4つの再発防止策を紹介します。
- 周囲を見落とさないための運転習慣を身につける
- 明るいLEDライトを装着する
- 車両の安全装備を追加する
- ドライブレコーダーを装着する
周囲を見落とさないための運転習慣を身につける

周囲の状況を正確に把握しながら運転する習慣を身につけることは、事故を未然に防ぐうえで欠かせません。
特に駐車時や後退時は、目視だけでなくバックミラーや後方カメラも活用し、複数の角度から安全を確かめることが重要です。
低い位置など目視では確認しにくい箇所も、カメラ映像を併用すれば見落としを防ぎやすくなります。
一方でモニター映像だけに頼ると、カメラの死角にいる歩行者や自転車に気が付かない可能性もあるため、ミラーや目視も組み合わせて周囲の動きを確認しましょう。
こうした確認の積み重ねが、見落としによる接触事故を防ぎ、安心して運転できる環境づくりにつながります。
明るいLEDライトを装着する

夜間や暗い場所での接触事故を防ぐには、視界を確保し、相手からも見えやすくする工夫が欠かせません。
そのために効果的なのが、明るいLEDライトの装着です。
LEDヘッドライトやLEDバックランプを使用すれば、従来のハロゲンランプよりも広範囲を照らすことができ、駐車場の柱や他車との距離を正確に把握しやすくなります。
加えて、自車の存在を周囲に知らせるためには、LEDのポジションランプやハザードランプも有効です。
歩行者や他車からの視認性が向上し、思わぬ接触を防ぐ実用的な対策といえるでしょう。
明るいLEDライトを装着することで視認性を高めることはもちろん、周囲から認識され、事故のリスクを根本から減らせます。
車両の安全装備を追加する

事故や接触のリスクを減らすには、運転技術だけでなく、車両の安全機能を強化することも重要です。
近年は「コーナーセンサー」や「踏み間違い防止装置」など、後から追加できる安全装備が充実しています。
例えばコーナーセンサーを装着すれば、駐車時に壁や他車との距離をブザーで知らせてくれるため、狭い場所での操作も安心です。
また、踏み間違い防止装置を追加することで、万が一の急発進を防ぐことができます。
ディーラー純正品のほか、国の認定を受けた市販品も登場しており、多くの車種で後付けが可能です。
愛車に安全装備を追加することで、運転時の不安を減らし、より安心して走行できる環境を整えられます。
ドライブレコーダーを装着する

ドライブレコーダーは、万が一の接触やトラブル時に原因を明確にできる心強い装備です。
走行中の映像と音声を自動で記録し、事故や接触の瞬間を客観的に残せるため、過失の有無や状況の特定に役立ちます。
特に、駐車中の接触など目撃者がいないケースでは、映像が唯一の証拠となることも。
「ぶつかった音がしたけれど、実際に接触したかわからない」という場合にも、後から自身の運転を見直すことができます。
トラブル時の対応を確実にし、不安を減らすためにも、ドライブレコーダーを装着すると安心です。
筆者が語る「車からぶつかった音がしたけど傷がない」時の体験談
前述の「車の故障や整備不良」でも触れたとおり、筆者が実際に体験した「車からぶつかった音がしたけど傷がない」時の状況をお話します。
ある日、愛車を停めるときに後方から軽い振動と共に「ドンッ」という音が車内に響きました。
とっさに私は「どこかにぶつけた(ぶつけられた)」と思い車体周辺を見ましたが、ぶつけた跡はなく、周辺にも車などはありませんでした。
その後、同じ出来事が何度も続きましたが、そのたびに確認しても傷など何も見られません。
不安になり、整備工場で愛車を確認してもらうと、リアデフオイル(4WDの車で、後輪の車軸を回す部分のオイル)を交換していないことが分かりました。
オイルが劣化したことにより、リアデフの動きが悪くなり、異音と振動を発生していたようです。
オイルを交換すると、車をぶつけたような振動と音はなくなりました。
このような出来事が起きて以降、車からぶつかった音がした際はクルマ本体や周辺を確認することに加えて、愛車の整備状況も確認するようにしています。
まとめ
この記事では、「車からぶつかった音がしたのに傷がない」ときに考えられる原因や確認方法、再発防止策を紹介しました。
音の原因は小石の跳ねや軽い接触などさまざまですが、故障や整備不良によって発生する場合もあるため、日頃からのメンテナンスが欠かせません。
見た目に異常がなくても、内部が損傷していたり、軽微な事故とみなされることもあるため注意が必要です。
接触を確認した際は、警察や保険会社に連絡し、落ち着いて対応しましょう。
また、運転時の安全確認に加え、LEDライトや安全装備を活用することで、同じようなトラブルを未然に防ぐことができます。